プレリュード
プレリュード
細やかな気遣いが人心の琴線をそっと鳴らす。幾つも幾つもそうした琴線を、そっと鳴らしてきた男であった。
河野順吉(79)――。
深川市長を九四年十月~〇六年十二月まで務めた。
「河野さんは元気にしているだろうか?」「昔、河野さんに『○○○』と声をかけられた」――。取材の折々、名もなき市井(しせい)の人々から今も河野の名がでる。
北空知新聞に入社した記者は、ほぼ一人残らず市長・河野からの激励のはがきを手にした。あいさつに行き、数日して社に郵送されてきた。筆まめな男である。
河野の人柄をほうふつさせるエピソードを一つ。多度志鷹泊であった夏のイベントの取材を終え帰社して原稿を書いていた。窓を叩く音――。市長・河野の運転手を務める男性職員が多度志名物の「開拓笹だんご」を手に笑顔で立っていた。河野の差し入れだった。日曜出番の取材。「ご苦労さん」の意味合いもあったのであろうか。
人を構えさせない独特の魅力がある。庶民の懐にすーっと入り、心の琴線をそっと鳴らし、その余韻を今も残す。それでいて、若年期に身を投じた青年団活動をベースに培った幅広い人脈と太い中央とのパイプ。隔てはなかった。
今なぜこの男なのか――?
晩節にいろいろとあった。されど、それをもって河野が成した功が否定されるものではない。
ただ、紛れようもない事実として、コメを中心に据えたライスランド構想を筆頭に河野市政が築いた土台の延長線上に今の深川はある。
表舞台から去っておよそ十一年。「河野さんに会ったらよろしく伝えて」「あたしみたいな者の話しでもね、ちゃんと聞いてくれてね」「うちらのこんなちっちゃな大会にでも顔を出してあいさつしてくれた」――。六十代より上の世代にとって河野への親しみ懐かしさは、古き良き深川への郷愁と重なるようだ。
そうした数多(あまた)の声を聞き、思いに接するうちに腹がかたまった。河野を取り上げるのは小紙の務め――と。
今年五月――。電話した。思いを告げる。「数日、お時間をいただきたい」。河野は返答を留保した。
ぶしつけな企画の申し込み、当然と受け止め待った。
お受けする――。三日ほど経ったろうか、河野から企画に協力する旨の快諾を得た。河野は、小紙の企画に応じた気持をこう言った。
「一番はなんといって市民さ! それと議会、市職員のみなさんが『深川』の未来を見つめ、私に力を貸してくれた。その感謝をね……」 市井の人々の心の琴線を鳴らし、"ミスター深川"とも称された河野順吉の歩んだ道を、その時代のにおいとともに"奏でる"。
<写真> 自身の思い出と重なる旧スポーツセンター・北の大地元気の泉キャンパスの建物を背にした河野= 17年7月16 日
Page 25
◇








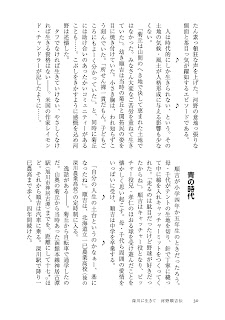






コメント
コメントを投稿